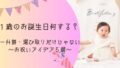お宮参りは終わったけど、次は百日祝い?お食い初め?これって別のもの?
食事にも決まりがあるみたいだけど、、、他の人はどうしてるのかな、、?
お宮参りが終わり少しすると、次は百日祝いとお食い初めという行事があります。
どんな行事なのか、何がいるのかなど悩みますよね、、、。
赤ちゃんが産まれて100日目を祝う「100日祝い(百日祝い)」と「お食い初め」。
『一生食べ物に困らないように』という願いを込めた。赤ちゃんの人生初めての大切な節目行事です。
最近では、レストランなどで行ったりするご家庭も増えていますが、「自宅で家族だけでゆったり祝いたい」という声は多いですし、百日祝いとお宮参りを一緒にするなんて方も増えています。(お宮参りと百日祝いを一緒にすることについてはまた別記事にしようと思います)
「お店に行かなくても特別な思い出を作りたい」
「親族とする自宅でのお食い初めのやり方を知りたい」
「伝統的にはしたいけど作るのが面倒」
「ちゃんと手作りしてあげたい、、でも時間もかかるな」
そんな方に向けて、作っても作らなくても、心温まるお祝いを成功させるポイントをさっさママの体験談も踏まえてまとめました。
お食い初めとは?意味と由来を簡単に解説
お食い初め(おくいぞめ)とは、赤ちゃんが”一生食べ物に困らないように”と願いを込めて行う、人生最初の食事の儀式です。
生後100日頃(地域によって差がある)に行うのが一般的で、「百日祝い(ももかいわい)」とも呼ばれています。
この行事は、平安時代から続く日本の伝統的な儀式で、赤ちゃんの健やかな成長を祈る大切な節目として、多くの家庭でも受け継がれています。
お食い初めと同時に、「歯固めの儀式」(丈夫な歯が生えるようにと祈る)も行います。
自宅での100日祝い・お食い初め
まず、昔からのこういった行事・儀式には地域によってどうしても差があります。
そこまでこだわらない・家族だけで行うのであれば気にする必要はありませんが、もし親族もご一緒に行うようであれば、親族やご近所の方、親しくしている方が近くにいるようであれば、決まったやり方があるかもしれないので、トラブルを避けるために事前に聞いてみるのも手ですよ。
昔は親戚や親しい付き合いのある知人を招待など多かったようですが、近年のお食い初めは、ママパパの両親意外に祖父母など家族だけで行う方が増えています。
場所は今回ご紹介している自宅、他にはホテルやレストランなどのお店を利用する方もいます。
百日祝いとお食い初めは必要なものが分かってさえいれば、ご自宅でも準備してできます。
必要な準備やアイテム
お食い初めの料理(祝い膳)基本1汁三菜→地域によって差があります
・鯛
→「めでたい」。長生きの象徴。物事を最初から最後までやり遂げるという意味も。
・赤飯
→赤は古来より魔除け災いを避ける力があるといわれている。邪気を払い健やかな成長を願う
・汁物(ハマグリのお吸い物):ハマグリは高価ですし、意味合い的にもしじみやアサリなどで も代用可能です
→吸う力が強くなるように。良い伴侶に恵まれるようにという意味もある。
・煮物(根野菜の煮しめなど)(人参、大根、かぼちゃ、れんこん、たけのこなど)
→縁起のいい食材を使用(飾り切り)それぞれに意味がある
・香の物(梅干し、酢の物など)
→幸のものとかけてこう呼んでいる
食器+祝い箸
→漆器のお膳(色に男女差があります。地域によっての差があるのでこだわる場合は要確認)
※近年では費用のことなどもあり、ご自宅での略式としてこれからも使えるよう離乳食用の食器をお食い初めの際に合わせてご購入されたり、元々あるものを使ったり、ご家庭によって様々な工夫がみられるようになっています。
祝い箸はダイソーなどにも売っていますので、安価に済ませることが可能です。
歯固め石(地域差あり)
→お宮参りの際にいただくこともありますし、お借りすることもできます。ない場合はネットやお店での購入もできます(梅干し代用可)(黒豆を使う地域も)
これは親族も一緒に行う場合ですが、、、
手土産
→クッキーなど
あると喜ばれますが、なくても全く問題ありません。
料理に関しては、自身で作る方法以外にも、百日祝い用のメニューをテイクアウトするという方法や、事前に通販で手配しておく方法などもあります。(この記事もまた載せますね!)
お食い初めで使用する食器の種類!漆器・陶器・木製などの特徴
まず、伝統的なお食い初めで使用する食器は漆器です。
その他、お食い初めの際使用されている食器の種類を以下にまとめました。
●食器の種類
漆器→木に漆を塗り重ねて作られたもの:割れにくいが、電子レンジや食洗器に対応していない
陶器→土などから作られたもの:温かみがあり電子レンジや食洗器対応もあり使いやすいが、割れやすい
木・竹製→木・竹で作られたもの:軽くて頑丈、シンプルだが、料理のにおいが染み込みやすい
ポリプロピレン製→プラスチック素材で作られたもの:割れにくく離乳食の食器向きだが、食器によっては耐熱性がない、絵柄がはがれやすいなどあり
男の子・女の子で違う?性別による食器の選び方
性別によって色が違う理由は、平安時代、地位を色分けしていたこと、男性が優遇されていたことが背景にあります。
地域によって色は逆の場合もあったりしますので、お住まいの地域などで確認は必要です。
【男の子の場合】
内側・外側ともに朱塗りの器(日輪や菖蒲の模様ありの場合も)、お膳は低いもの
【女の子の場合】
外側が黒塗りで、内側が朱塗りの器(花模様や束ねのしの模様ありの場合も)、お膳は高いもの

レンタルと購入どっちがいい?向いているのはどんな方?
★レンタル
・一度きりでしっかり伝統的に行いたい
・漆器は使いたいが、管理はしたくない
・伝統的にはしたいが、費用を抑えたい
・レンタルに抵抗がない(多少傷や使用感がある場合などもある為)
★購入
・今後も食器として使いたい
・行事などで使う可能性あり(漆器の場合)
・行事としては行いたいが、そこまでかしこまったものでなくていい(漆器以外の場合)
・返却するのが手間
・伝統的にではなくていいので費用を抑えたい(百均などでそろえる方法もあります)
※方法として、手作りをせず、お食い初めセットとして食器もついているセットの活用もあります。(別記事あり)
さっさママの料理+体験談

さっさママ初めての子の百日祝いとお食い初めは、自宅で「両家の両親」と「義祖父母」を招いて行いました。
食器は義祖父母からお借りしていたものを使用。(元々離乳食用の食器予定でしたが、義実家の家庭ではだめだったようでお借りすることに。どこまでゆるくしてもいいのかはなるべく確認が必要ですね)
祝い箸、鯛の飾りはダイソーで購入。(当時と商品が変わっていると思うので、また便利だなというお店や安い、おすすめだなという通販などを探して今度記事にしますね!)
鯛やお赤飯、煮物系の時間がかかるものは先に作っておきました。
(煮物はカボチャとレンコン、人参、シイタケを飾り切り)
残りの香の物は、大根と人参の酢の物。汁物はその日に作って完成。
(黒豆は作り置きしてくれていたものを使用)
お宮参りでいただいていた石も準備。
全員でご飯の予定だったので、量的にも足りないと思いスシローでお寿司をテイクアウトしてありました。
親族が集まり、準備が整ってからいざ!
(ちなみに赤ちゃんの服装は少しきれいめなワンピース、他の大人はセミフォーマルで堅くなりすぎないような服装にしていました。)
さっさママの子は女の子だったので、この時は義祖母が養親者でした。
周りが支えながら順番に行いつつ、その間に写真を撮ったりしましたよ。
その後歯固めの儀式も行い、カメラのタイマー設定で全員の写真を撮りました。
すべて終わった後は、ご飯をみんなで食べて、お土産をお渡しして、義両親、義理祖父母とお別れ。
全ての片付けをして終了。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
食事の配置についてだいたいこんな感じだったというものです。
地域差もありますし絶対ではありませんが、ご参考までに。

ちなみに娘の百日祝いの写真を後日撮りに行きましたので、そちらの記事もまた載せますね!
当日の儀式のやり方や注意点
お食い初めの儀式は順番があります。
①赤ちゃんに食事をあげるマネをします。
この時、赤ちゃんに食事を食べさせる役割を担う人のことを、養い親といいます。
伝統的には、長寿にあやかるという意味合いから、参加者の中で、赤ちゃんと同じ性別+最年長者が務めます。(最近では順番にしたりするご家庭もあったりさまざまです)
「ご飯→吸い物→ご飯→焼き魚→ご飯→吸い物」の順で祝い箸で、赤ちゃんの健康と赤ちゃんの口元へもっていきます。食べさせるマネなので、唇にあてていくだけで大丈夫。
これで合ってるのかなと不安になるかもしれませんが、合ってます!
この順番を3回繰り返したら、最後に歯固めの儀式を行います。
※順番を間違えてももちろん大丈夫!
そのまま続けてもいいし、もう1回でも、笑顔で仕切り直せば問題なし。
目的は赤ちゃんの健やかな成長を願うことです!
②歯固めの儀式
歯固めは、用意した小石にお箸でふれ、次に赤ちゃんの歯茎にちょんちょんと当てます。
小石もちょんちょんと当てるだけでOK!
※注意
お子様が誤って飲み込んでしまわないように大人は注意が必要。
アレルギーなどもまだわからないので、口元に少しあてるだけでOK
③写真撮影
儀式の途中にも行うので
④儀式終了後は、大人たちで願いを込めながら祝い膳をいただきます
④解散
※来られた際にお祝いをいただくこともありますので、感謝を伝えて受け取りましょう。
作らない方法をご紹介
ここまで、手作りの方法をお伝えしてきましたが、決して手作りではないといけないということはありません!ここからは、外食やデリバリーで叶える”今どき”のお食い初め、”作らないお食い初め”のお祝いをスムーズに行うためのポイントや、おすすめの準備アイデアをまとめました。
自宅で手作りをしてするお祝いが大変と感じる理由
- 赤ちゃんを気にしながらの作業になる
- 準備が多く、手間もかかる(家の掃除や飾りつけ・器や料理の材料準備など)
- 料理の種類、流れ、作り方、行事の進行方法など悩みが多い
- 写真映えや雰囲気作りが難しい
- 後片付けが負担
- 親族参加の場合は、お食い初めメニュー以外にも食事の準備や好みのリサーチなども必要になり負担増
など、理由もさまざまです。
外部サービスを活用する2つの選択肢
・外食:レストラン・料亭
・注文:ネット予約・仕出し・宅配
お食い初めを外食で行うメリットデメリット
メリット
- プロの料理と器で本格的なお祝いができる(場所によるがアレルギー対応ありの場合も)
- 家族分のご飯も準備できる
- 進行など気にする必要がない(お食い初めのプランなどの場合儀式の進行サポートがある場合もあります)
- 特別感がある
- 片付け不要
デメリット
- 予約した上で車の移動になる可能性が高いので、赤ちゃん・家族の体調+安全+スケジュール管理が大切(移動時の負担が大きい・感染症などの心配)
- 授乳のタイミングや赤ちゃんのご機嫌が気になり気を遣うことも
- お店の雰囲気やスペースによっては、撮影が制限されることもある
- 費用がかさむ
- キャンセル料の発生の心配
お食い初めをデリバリーで行うメリットデメリット
メリット
- 自宅でリラックスして行える
- 先にゆっくり吟味して選ぶことができる
- 家族分も同時に頼むことができ、注文すれば他にしないといけないことはほとんどなくなる
- お食い初めのプランに流れの説明書などが入っていたり追加のサービスも
デメリット
- 儀式の厳格さが薄れる可能性(地域や風習のずれなど)
- 料理の見栄えが劣る可能性(配送によって崩れたり、温度が下がったり)
- 費用がかさむ
- 体調不良でのキャンセルが難しい
- 冷凍ではない商品だと日持ちがしないため、配送時間等の調整が必要
- 地域により仕出しや宅配に差がある
どっちが我が家に合う?選び方のポイント

①予算
②赤ちゃんの体調
③誰と行うのか
④参加人数や住んでいる場所・交通手段
③赤ちゃんの体調
④当日の動きのイメージ
⑤ママ・パパがどうしたいのか
これらを踏まえて、しっかり考えるのがおすすめです。
外食とデリバリーを両方使う方法もあり!
→親族と一緒に外食・自宅では家族だけでデリバリーなど
手作りしていないことにどうしても罪悪感を感じてしまう時は、汁物だけ作ったり、”何か一品足す”というのもおすすめです!
まとめ

お祝いってつい『ちゃんとやらなきゃ!』って思いがちですが、一番大切なのは、”その時間を家族で笑顔で過ごすこと”です。
100日目という節目を迎えられたこと、それだけでも本当に素晴らしいことです!
かたちにとらわれて、頑張りすぎなくて大丈夫。
無理せず、できる範囲で、どんなかたちでも赤ちゃんを思う気持ちがあれば問題ありません。
子供の為にしてあげたいという気持ち、そして調べて悩んでいるその時間、それだけでママパパの愛情は十分伝わると思います。
形式よりも無理なくできることが大切。笑顔ある中で、みなさんがお子様の成長を喜びながらお祝いする、今後の赤ちゃんの成長に思いをはせる、それが一番大切なことだとさっさママは思います。
どちらにも良さがあるので、状況やどうしたいかなどを考えて、外食とデリバリーなどを比較・検討して、上手く外部サービスを活用していただきたいです。
初めて尽くしの行事、赤ちゃんとママパパの今しかない大切な瞬間が、後悔なくたくさんの笑顔溢れる楽しい思い出になりますように。